円満退社を目指そう!スムーズに退職するためのポイントを徹底解説

退職は人生における大きな決断の一つですが、スムーズに新しいステージへ進むためには「円満退職」を目指すことが大切です。
せっかくなら、トラブルを避けて気持ちよく次のステップに進みたいですよね。
「どうすれば円満退職ができるの?」
「退職の流れや手順がわからない…」
「トラブルを防ぐには何を準備すれば良いの?」
この記事では、こうした疑問にお答えしながら、円満退職のために必要な準備や具体的な流れ、トラブルを避けるコツを詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 円満退職をするための基本的な流れ
- 退職時に必要な準備や心構え
- トラブルを防ぐ具体的な方法
- 最後まで誠実に対応するためのポイント
退職は新しいスタートの第一歩です。この記事を参考に、感謝の気持ちを忘れずに円満退職を目指しましょう。
気になる項目からぜひチェックしてみてください!
目次
円満退職とは
円満退職とは、会社や同僚との関係を良好に保ちながら、トラブルなくスムーズに会社を辞めることを指します。
ただ単に退職するだけでなく、これまでお世話になった人々に感謝の気持ちを伝えつつ、責任を持って業務を引き継ぎ、後腐れなく新しいステップへと進む状態を指します。
円満退職を実現するには、いくつかのポイントがあります。
まず、直属の上司や関係者に誠実な態度で退職の意思を伝えることが大切です。また、退職理由を明確に伝え、引き止めにくい理由を選ぶことでスムーズな交渉が可能になります。
さらに、業務の引き継ぎをしっかり行うことも欠かせません。
後任者や同僚が困らないよう、マニュアルの作成や進捗状況の共有を積極的に行うことで、感謝されながら退職できる可能性が高まります。
円満退職を果たすことで、職場での評判が保たれ、場合によっては元の会社との良好な関係を維持したままキャリアを進めることができます。
将来どこかで再び関わる可能性も視野に入れ、最後まで責任を持った対応を心がけましょう。
円満退職に関するSNSでの体験談
ネガティブな意見
円満退職でしたが、有休消化は手持ちの4分の1程度でした。 今思えば、多少周りから疎まれようとも、全消化しておけば良かった、とも思います
直接伝えて、円満に退職できれば良いですが、そうではない会社もあるため、退職代行を利用もやむを得ない場合があります
円満な退職、本当に存在するのか疑問
会社を円満に退職できる方法、寿退社しかない
円満とは言えなかっただけに、あれから上司と会話をすることが殆ど無くなった。
ポジティブな意見
有給消化の件、退職日前に一気に全部消化できることになりました。
新居、引越し、転職先とトントン拍子で決まり、現職への退職申し出もありがたいくらい円満に済み、離婚関連の手続も着々と。
転職活動してましたが無事内定貰えて実は年内には内定→今の会社に退職届けを提出し今は諸々準備だったり引き継ぎを行ってまして円満退職出来そうです
家の近所ですし、円満退社なので特段どうこうはないのですが、一緒に働いてた子たちと中華料理屋で梅酒飲んでバカ笑いして帰る。最高に良い1日でした。
円満退職への9つのポイント
退職の理由を明確に決める
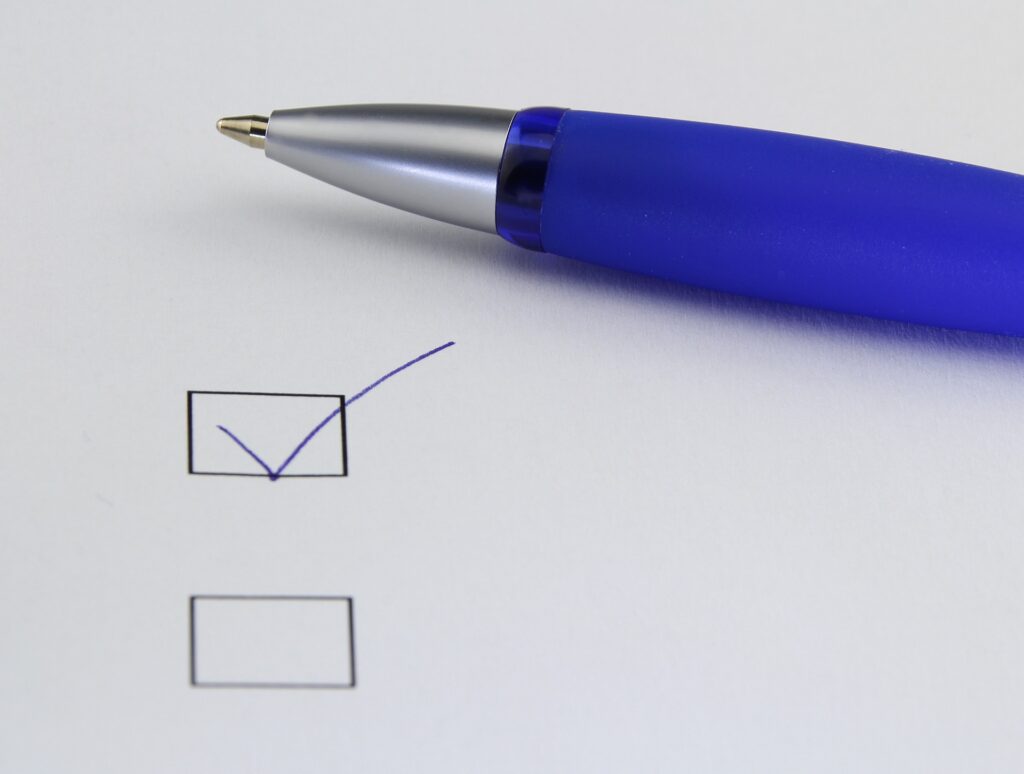
上司に退職の相談をした時に退職の理由は必ず聞かれます。
曖昧でよくわからない返答をすると退職トラブルの理由になりますので事前にしっかりと考えておくことが大切です。
退職理由に嘘をつくことはオススメできません、後々つじつまが合わなくなってしまい良くない印象を持たれたり、変な噂を流されるようなことになってもいけません。
退職理由が曖昧だと、引き止められることも良くあります、引き止められにくい理由を考えておく事が必要です。
退職トラブルにならないように会社への不満を理由にしない方が良いでしょう。
退職時に引き止められにくい理由
- 体調が悪くて仕事を続けることが難しい
- スキルアップしたい
- 上のポジションで仕事をしたい
- 自社ではできない違う分野にチャレンジしたい
- 他の分野で頑張りたい
- 結婚・出産・子育てに専念したい
- 家族の介護など
- 独立開業
ちなみに私の以前の退職の際は、下記の説明だけで多少引き留められましたが、最終的には円満退職できました。
- 「体調がとても悪く退職してしばらくの期間ゆっくりしたい」
- 「先のことは全く考えていない」
また、業務の引き継ぎなども考えておき、引き継ぎ可能なことを伝える準備もしておきます。
有給日数の確認をする

退職の理由を決めたら、有給休暇の残日数を確認することをお勧めします。
給与明細に有給の記載や有給管理表などがない場合は、事務の人に有給の残日数を確認してください。
多い方では最大40日程度になると思いますので、通常の休みと合わせると給料を貰いながら約2ヶ月程度休めることになります。
有給休暇は労働者の権利なのでしっかり取得して退職をしましょう。
退職日までの期間が短く引き継ぎなどができない場合は、有給を取得しにくくなる場合もあるので、余裕を持った退職日の設定が大事です。
退職日を決める

転職先の入社日や有給休暇の消化や引き継ぎの段取りなどを踏まえて退職日を決めましょう。
退職届を提出日から最低でも1ヶ月の期間はとるのが一般的です。
また、会社の繁忙期などを避けるなどの配慮も大切です。
ここまでが退職の事前の準備になります。
退職の相談は直属の上司にする

退職日の2〜3か月ほど前に直属の上司に対面して口頭で退職の相談をしましょう。
いきなり書面やメール・ラインなどで伝えることはオススメしません。
文字だけで伝えようとすると、本来の意図が伝わらず誤解を招くこともあります。
また上司に退職の相談をするまでは、同僚には退職のことは伝えないことも大切です。
転職が決まっている場合も、転職先については言わない方が良いでしょう。
上司が他の職員から事前に退職の話を聞いてしまうと不快に思われることもあるからです。
退職届を直属の上司に提出する

退職日から1ヶ月以上前に退職届を直属の上司に提出をします。
「退職届」は退職する届出、「退職願」は申し入れなので上司承認が必要なので、退職する意思がはっきりしている場合は退職届を提出します。
退職届に必要な項目
- 退職願
- 一身上の都合により
- ○月○日をもって
- 退職いたします
- 氏名(部署/自分の名前/印)
- 宛名(会社名/代表取締役○○殿)
業務の引き継ぎをする

業務の引き継ぎについては、会社からの指示がない場合はまず直属の上司に相談をしましょう。
自分の業務を伝えて、どの業務を誰に引き継いでいくのか確認をしましょう。
引き継ぎ計画書など業務をリスト可して、引き継ぎの状況を上司に複数回経過報告すると良いでしょう。
事前に自分の業務の棚卸しをしておくとスムーズに引き継ぎができます。
転職以外でも、日頃から自分の業務をリストアップしたり、マニュアル化しておくと業務が整理されてよりスマートな仕事ができます。
在職中に引き継ぐことが基本ですが、可能な範囲で、退職後も1ヶ月程度は可能な限りメールなどでのサポートをする旨を伝えておくと上司や後任者の不安は解消されるでしょう。
関係者へ挨拶をする

退職日まで1ヶ月を切ったら、関係者へ挨拶をしましょう。
相手先に合わせて、電話かメール等でするのが一般的です。
関係者への挨拶で必要なこと
- 退職のご挨拶
- 退職日
- 最終出社日
- 後任者
会社へ返却するものを会社に渡す

会社へ返却するもの
- 身分証、名刺、社員証、制服など
- カギ、セキュリティキー
- 通勤定期券
- 健康保険被保険者証
- パソコン、スマホなど
退職日までに会社から貸与されているものは、忘れず返却しましょう
退職する会社から受け取るものを受け取る

退職の際、会社から受け取るもの
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳(会社が保管している場合)
離職票
会社を退職した際にハローワークでの求職の申し込みや失業手当の申請をする際に必要な書類で会社が手続きをしてハローワークが発行する
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入した際に発行される証明書、会社を退職する際に渡されることが多い
源泉徴収票
会社が支払った給与など総支給額と支払った所得税額を証明する書類
年金手帳
公的年金制度に加入していることを証明する書類
退職に向けた心構え:感謝の気持ちを忘れずに
退職は新たなスタートを切る大切な節目ですが、これまでお世話になった会社や上司、同僚への感謝の気持ちを忘れないことが大切です。
どんな形であれ、現在のあなたがあるのは会社や一緒に働いた人々との関わりがあったからこそ。
その感謝の気持ちをしっかりと伝えることで、気持ちよく次のステップに進むことができます。
円満退職の鍵は、最後まで誠実な対応を心がけることです。
たとえ退職の理由がネガティブなものであっても、会社や同僚に対するリスペクトを持った言動を意識しましょう。
具体的には、業務の引き継ぎを丁寧に行う、退職時の挨拶をしっかりするなど、最後まで責任を全うする姿勢が重要です。
このような姿勢が、将来どこかで再び関わるかもしれない人間関係を良好に保つカギにもなります。
退職は一つの終わりであると同時に、新しい挑戦への始まりでもあります。
これまでの感謝を胸に、気持ちよく次のステージへと進みましょう。
トラブルが発生した場合の対処法
退職時には、思いがけないトラブルが発生することもあります。例えば、以下のようなケースが挙げられます:
- 退職届を受け取ってもらえない
- 業務の引き継ぎで過剰な負担を押し付けられる
- 退職を強く引き止められる
こうした問題に直面したときに冷静に対処するためには、事前の準備や適切な対応方法を知っておくことが重要です。
退職届を受け取ってもらえない場合
会社側が退職を拒否するのは法的に許されません。
法律では、退職届を提出すれば最短2週間後には退職が可能です。受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で送付する方法もあります。
労働基準監督署や転職エージェントに相談するのも有効です。
引き継ぎの負担が過剰な場合
引き継ぎは退職者としての義務ですが、過剰な負担を強いられる場合は上司に相談しましょう。
対応が難しい場合は、「できる範囲で最大限努力する」という姿勢を示しつつ、無理のないスケジュールを提案することが大切です。
退職を引き止められた場合
退職の意思が固い場合は、明確な理由を伝えてブレない姿勢を保つことが重要です。
引き止められる際に感情的にならず、穏やかかつ丁寧な態度で話すよう心がけましょう。
転職先が決まっている場合は、「具体的な予定があるため、退職は変えられない」と説明すると効果的です。
どうしても退職が進まない場合は、退職代行会社の利用も検討すると良いでしょう。
あわせて読みたい


【厳選比較】即日退職するためにおすすめの退職代行サービス31選|料金や内容を徹底解説
退職を考えている中で、なかなか退職を言いづらいケースがあります。 退職をしたいけど上司に言いづらい 何度も退職の話はしたけどはぐらかされる 今すぐ会社を辞めたい…
トラブルを防ぐためのポイント
- 就業規則を確認する:退職手続きに関するルールを把握しておきましょう。
- 事前に相談する:トラブルが起きそうな場合は早めに上司や人事に相談するのが得策です。
- 外部の専門家に相談する:労働基準監督署や弁護士、転職エージェントのサポートを活用するのも有効です。
退職時のトラブルは誰にでも起こり得るものですが、冷静に対応することで解決に近づけます。
事前の準備と柔軟な対応を心がけ、スムーズな退職を目指しましょう。
事前準備をしっかりとして円満退職をしよう!
以上、円満退職に向けての流れと準備、トラブルを減らすポイントになります。
今まで雇ってもらい、成長することもできた感謝の気持ちや、今後の自分のスキルアップなどポジティブな内容を伝えることを意識するとお互いにとって良いでしょう。
今までお世話になった会社へ最後まできっちり対応をすることが、今後のあなたの仕事にも良い方向へ向かうと信じて、円満退職を目指して最後までやり切りましょう。
円満退社をするのが不安な人は、転職エージェントを利用すると退職のサポートも手伝ってくれるのでおすすめです。
無料で「転職相談」「応募書類の添削」「面接対策」「年収交渉」などをしてくれます。
最大のメリットは一般のサイトにはない自分の希望と条件に合う「非公開求人」の紹介をしてくれるので仕事などで忙しい方も効率的に条件の良い求人を探すことができます。
円満退職をするのにおすすめの転職エージェント
▼【総合型】おすすめの総合型転職エージェントランキングはこちら
あわせて読みたい


【徹底比較】年代別の登録するべきオススメ転職エージェント|20代・30代・40代
転職は人生の中でもライフスタイルを変える大きなターニングポイントになります。 転職を考えている人はそれぞれの人によってさまざまな理由があると思います。 年収を…
スクロールできます
| サービス | ジェイック 就職カレッジ | doda (デューダ) | ワークポート | WorX (ワークス) | リクルート エージェント |
|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ ポイント | 正社員求人のみ 未経験・フリーター 第二新卒に強い | 約16万件の求人 スカウトが届く | 全国に求人が豊富 | 未経験異業種転職 年収平均90万円up | 求人約50万件は 業界1位 |
| 特徴 | 就職成功率81.1% 入社後定着率91.5% 就職実績2.3万人以上 | 無料診断ツール充実 優良求人多い 転職イベント・フェア | 相談実績50万人 | 200時間のスキル アッププログラム | 求人数:業界1位 転職実績41万人 |
| 公開求人数 | 非公開 | 156,450 | 113,939 | 3,000 | 365,610 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 268,817 |
| おすすめ度 | |||||
| 主な対象年代 | 18〜39歳 | 20代〜50代 | 20代〜40代 | 18歳〜35歳 | 20代〜50代 |
| 対象エリア | 全国 | 全国、海外 | 全国 | 全国 | 全国、海外 |
| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 |
| 公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コメント